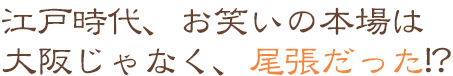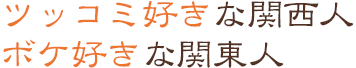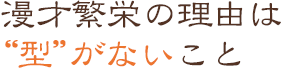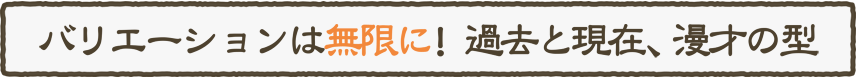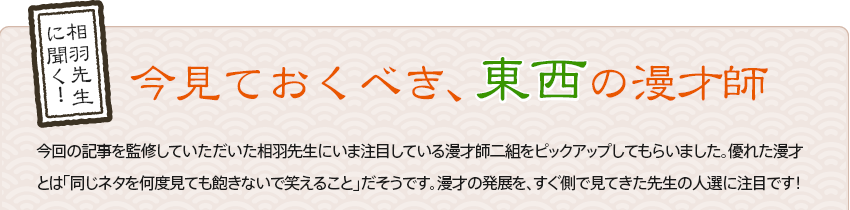時代に合わせ、柔軟にその形を変えてきた漫才。その歴史上には、数々のエピソードが残されています。
ここでは、思わず人に話したくなるような、知られざる漫才トリビアをご紹介します!
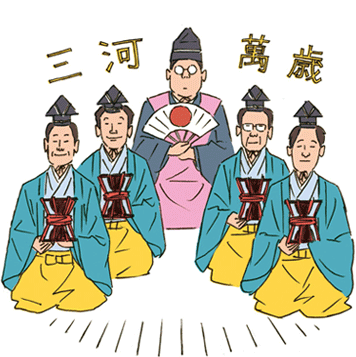
漫才の本場と言えば大阪! これに異論を挟む人はいないでしょう。しかし、江戸時代、愛知県の尾張地方がその中心だった時期があるのです。先に「萬歳」を紹介しましたが、中でも絶大な人気を集めたのが愛知県の三河萬歳。きっかけは1594年に豊臣秀吉が京や大阪で芸事を生業にしている人たちを、荒地開墾のために呼び寄せたこと。秀吉の死後も、この地に残った彼らは、その芸の質の高さもあって、多いに人気を集めました。特に徳川家康が彼らを溺愛し、17の県を巡礼する権利を与え、関東一円にまで勢力を拡大。「江戸の萬歳=三河萬歳」と言われるまでに発展しました。この三河萬歳(現在は万歳)は国の重要無形民俗文化財に指定されており、今でも鑑賞することができます。

関東と関西の笑いの違いを考えたとき、ポイントになるのが「ツッコミ」です。関東の人はボケた瞬間に笑い、関西の人はツッコミを待って笑うという違いがあるそうです。そのため、関西で受けるのはツッコミのうまいコンビ、東京で受けるのはボケがおもしろかったり、キャラクターが突出しているコンビという傾向が見られます。現状、関西で売れて関東に出てくるという流れが主流になっていますが、その際にツッコミの度合いを調整するコンビも少なくないとか。今後、場所と観客の反応の関連を見ながら漫才を見ると、いつもと違う一面が発見できるかもしれません。
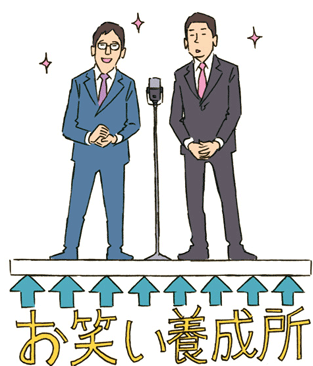
漫才が世に広まった要因の一つが、養成学校の存在です。それまでは、師匠に弟子入りすることが唯一の入り口でした。人気の漫才師に弟子入りするために何年も待つこともあったそうで、非常に門戸が狭いものでした。もっとも古いお笑いの養成所は1968年に設立された松竹芸能タレント養成所でした。その後、1977年に人力舎のスクールJCA、1982年には吉本総合芸能学院(NSC)が開校。弟子入りからではなく、養成所で相方を見つけ、バックアップを受けながらデビューするという流れが一般的になっていきました。育成環境が整備されたことが、漫才を大きく成長させた原動力だったんですね。

落語や能、狂言など、伝統的な芸事の中で、「漫才」ほど私たちの日常生活に根付いているものはありません。その理由の一つが「型がない」こと。落語であれば一人の人間が着物を着て座って…という型があり、能や狂言にもそれはあります。型があるからこそ魅力がある一方、変わり続ける時代に柔軟に対応しづらいという側面もあります。その点、漫才には固定の「型」がなく、時代に合わせた柔軟なスタイルが生まれやすいという利点があります。漫才は時代の空気を反映し、凝縮させた芸。今の漫才師がラフな普段着で漫才に望んだり、ダブルボケやダブルツッコミがあったりと、バリエーションに富んでいること自体が漫才繁栄の理由なんですね。
しゃべくりを基本とする言葉の掛け合いが漫才の特徴。しかし、長い歴史の中には、思わず目を疑うようなネタもあったようです。ここでは、過去に存在した前衛的なネタと現役で活躍中の新しい漫才スタイルを見ていきましょう。
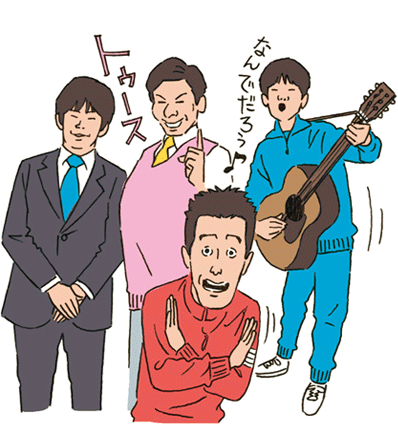
● ゴリラ漫才…林家染団治・小川雅子
● ボクシング漫才…中田ダイマル・ラケット
● タコ漫才…漫画トリオ
● ホラ吹き漫才…横山たかし・ひろし
● ボヤキ漫才…人生幸朗・生恵幸子
● いきり漫才…NON STYLE
● ズレ漫才…オードリー
● ノリボケ漫才…ハライチ
● 貴族漫才…髭男爵
● あるある漫才…テツandトモ
● スケッチブック漫才…いつもここから
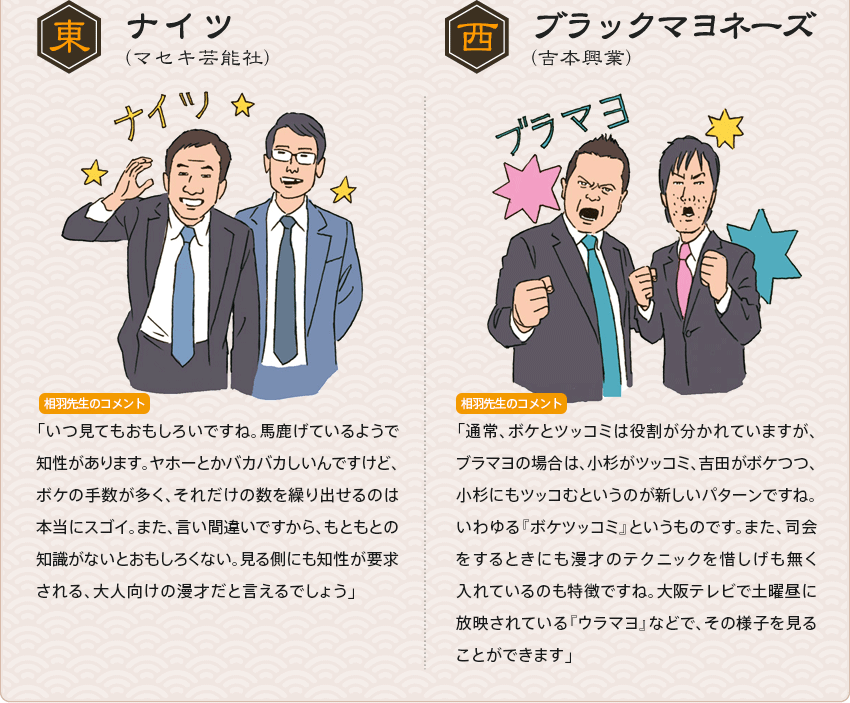
多くの人に愛され続けてきた漫才。その裏には様々な出来事や人のチャレンジがあったんですね。
この幅の広さこそが、漫才繁栄の理由なのかもしれません。
そして、今回は相羽先生のオススメにも挙げられていた、東の雄・ナイツへの特別インタビューを敢行!
彼らの漫才への熱い思いを聞きました!

-
取材協力
相羽秋夫/演芸評論家・放送作家
演芸評論家・放送作家。1966年同志社大学卒業後、松竹芸能(株)に入社。日本のお笑いブームの隆盛を支える。その後、大阪芸術大学にて教授、芸術計画学科長を歴任。「M-1グランプリ」では、第1回から第6回までの大阪予選審査員も務める。現在は日本笑い学会副会長、上方演芸研究家・評論家として活動する傍ら、文化庁芸術選奨、文化庁芸術祭賞、大阪文化祭賞、上方漫才大賞などの審査員も務める。