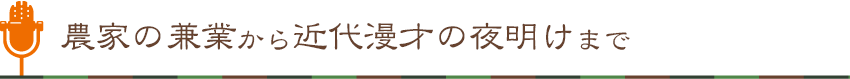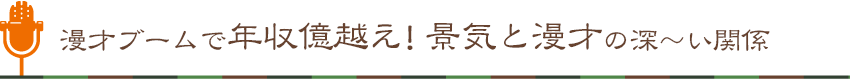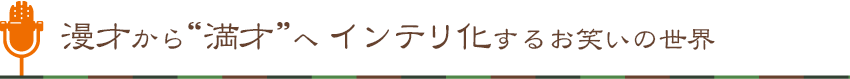特にお笑い好きではなくても、普段の生活で「ボケ」や「ツッコミ」を意識している時ってありますよね。
もともと漫才由来のこの言葉。一つの芸で使われていた言葉が、これだけ世間に定着してるってスゴイことだと思いませんか? 落語や能、歌舞伎など、いろいろな芸がある中で、「漫才」がココまで愛されているのには、何かしら理由があるはず。今回は漫才のルーツを辿り、その本質を探ります!

漫才のルーツは、平安時代にはじまり、今も全国各地に伝わる「萬歳」という伝統芸能です。これは農業に携わる人々の農閑期の仕事として、素襖・風折烏帽子に腰鼓を着けて家々を訪問し、鼓・三味線で祝言を述べ、その報酬を得るという「門付芸」を主としていました。基本スタイルは、太夫(たゆう/興行権を持っている人)と才蔵(さいぞう/太夫が雇う人)の2人1組。当時から役割分担がなされていたようで、太夫がツッコミ、才蔵がボケ。これが、今日のボケツッコミの原型となっています。

昭和初期の頃には、それまで歌や舞のつなぎとしてしか考えられてこなかった「おしゃべり」を全面に打ち出したコンビが誕生しました。これが、横山エンタツ・花菱アチャコのコンビです。この2人は“近代漫才の父”と呼ばれ、現在の漫才スタイルの先駆けと言われています。時を同じくして吉本興業の文芸部長だった橋本氏が、その頃流行していた「漫画」に注目。「萬歳」の略字であった「万才」に漫の字を当て、「漫才」という言葉が生まれたのです。この当時、吉本興業の宣伝部が発行した「吉本演藝通信」で改称が宣言され、全国的に「漫才」という言葉が広まっていきました。
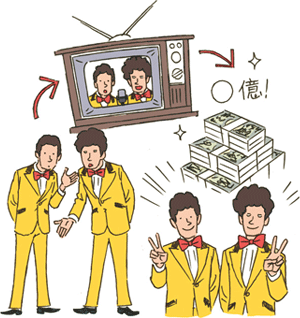 その後の漫才の繁栄は皆さんの知っての通り。1980年頃にはテレビを中心にした漫才ブームが到来。ツービートやB&Bなどの国民的スターが生まれました。この当時の彼らは数億円もの年収を稼いでいたとも言われ、漫才師が若者にとって憧れの職業になっていきました。ギャラ高騰に関しては、テレビの影響が大きく、「バラエティに出てお茶の間に顔が売れる→営業が引く手数多になる→地方営業を行い、さらに人気が出る→テレビのレギュラー獲得」という好循環が生み出した賜物でした。この流れは現在も続いており、人気を獲得する人とそうでない人の顕著な二極化が進んでいます。
その後の漫才の繁栄は皆さんの知っての通り。1980年頃にはテレビを中心にした漫才ブームが到来。ツービートやB&Bなどの国民的スターが生まれました。この当時の彼らは数億円もの年収を稼いでいたとも言われ、漫才師が若者にとって憧れの職業になっていきました。ギャラ高騰に関しては、テレビの影響が大きく、「バラエティに出てお茶の間に顔が売れる→営業が引く手数多になる→地方営業を行い、さらに人気が出る→テレビのレギュラー獲得」という好循環が生み出した賜物でした。この流れは現在も続いており、人気を獲得する人とそうでない人の顕著な二極化が進んでいます。
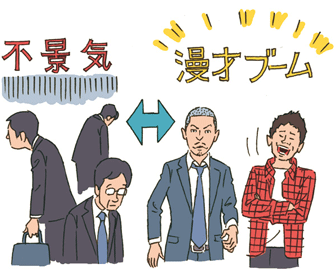
また、漫才の歴史を見て行くと、ある法則に気付きます。例えば、1962年〜69年の不景気と演芸ブーム、バブル崩壊後のダウンタウン、とんねるず、ウッチャンナンチャンなどの「お笑い第三世代」の人気。さらに、M-1グランプリがスタートした2001年頃もITバブルの崩壊と、不景気と漫才ブームが連動しているのです。これについて、一つは「お金がかからない遊びを楽しみたい」という消費者側の理由、もう一つは「テレビの制作費を抑えたい」という作り手側の理由が考えられます。不景気になり、世の中の気分が淀んでくると、自然に笑いを求めるという側面もありそうですね。
ロザンの宇治原(京都大学卒)、ますだおかだの増田(関西外国語大学卒)など、ここ最近テレビでは高学歴の芸人が活躍しています。ここに来て学歴が取りざたされている要因の一つが、観客の求めるレベルが上がったこと。漫才の裾野が広がり、お笑いの知識も豊富と来れば、単純な笑いやダジャレでは太刀打ちできません。そういった客層にウケるネタを模索し続けた結果、漫才師にも知性が求められるようになってきたのです。おもしろいという意味で漫画から取られた漫才の“漫”という文字は、今後才能や知性が満ち溢れる、という意味での“満才”に変わっていくとも言われています。
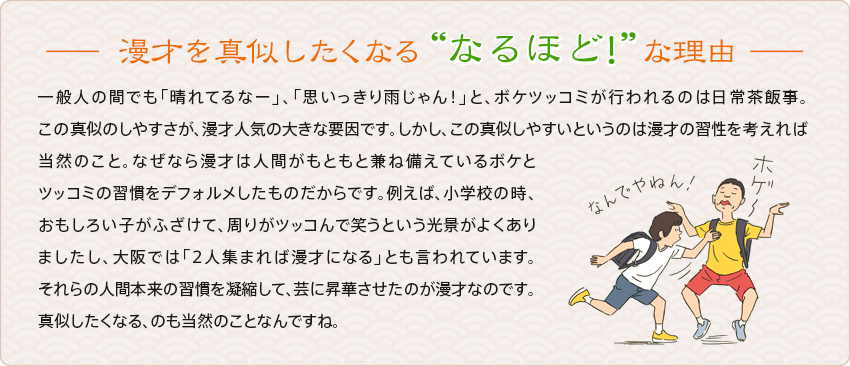
「萬歳」から「漫才」を経て、「満才」へ。人々の生活に根ざした笑いは時代に合わせて進化を続けています。
だからこそ、いつの時代も漫才は愛され続けているのでしょう。そして、私たちが漫才を愛する理由には、
その構造自体が「人間の習性」だったことが関係しているんですね。
次のページでは、思わず人に話したくなる、漫才トリビアをご紹介します!